修理は組立て側の作業に入っていきます。本底と中底の間を埋める「中もの」にはクッションのような役割がありますが、完成時に靴底の凹凸を美しく演出する機能もあると私は考えています。バーウィックは良い靴ですが、靴底の凹凸に自分の好みを表現するために、オリジナルと異なる中ものを入れます。
「中もの」にチョットした仕込みをします
土踏まず~かかとの中ものはオリジナルのコルクから革に変更します。新聞紙を使って取った形に合わせて、剥がした本底を切り出します。

現物合わせで形状や厚みを調整してから、両面を木ヤスリで荒らして接着の下地を作っておきます。

貼り付けました。スッポリ収まっています。

残った前半部は、板コルクを貼って削ることで「みっちり」と埋めます。

中ものを革に変更した理由は、土踏まずに「モッコリの素」を仕込むためです。もちろん、これも剥がした本底から切り出して作りました。

本底を貼り付けます
本底との接着面、特にウェルトは古い接着剤をキチンと除去しておきます。毛羽立った状態にして、いわゆる「アンカー効果」を引き出すためです。

今回は靴が大きいので本底用の革を切り出す必要がありませんが、この後の細工がしやすいように、こちらの記事でご紹介した方法で型紙を起こしました。

目印の線を引きながら本底の設計(?)をして、加工を入れます。
土踏まずが華奢に見えるのが好みですので、コバが薄くなるように3ミリの厚さまで漉いておきました。
加工が終わったら、接着する箇所を木ヤスリでしっかりと荒らします。

ゴムのりを塗って乾かしてから水を付けて柔らかくして本底を貼り付けます。
最近は、この工程で靴底の凹凸と滑らかさを決めるように心掛けていますので、こくり棒で擦っている時間がドンドン長くなっているような気がします・・・

靴底面の形が決まったら、コバを別たちで切り回して整えます。ウェルトを削らないように、でもギリギリまで追い込むようにしています。


このあたりまで作業が進むと、思いが入るのと同時に、靴全体がシャンとし始めるように感じます。
そうやって気持ちが盛り上がった頃に「だし縫い」を迎えるのは、毎度ワクワクします。はやる気持ちを抑えつつ、今回はここまでです。
最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございます。







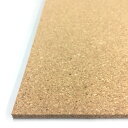





コメント